 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
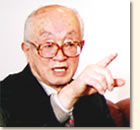
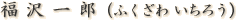
明治31年〜平成4年(1898〜1992) 洋画家 本名同じ
1898年(明治31年) 後の富岡町長、福沢仁太郎の長男として群馬県富岡町(現富岡市)に生まれる。
1915年(大正4年) 旧制富岡中学校を卒業、旧制二高英法科を経て、1918年(大正7年)に東京帝国大学文学部に入学したが、次第に大学から遠ざかり彫刻家朝倉文夫のアトリエを訪ね入門。
1922年(大正11年) 第4帝展彫刻部に入選、彫刻家としてスタートを切るが、1924年(大正13年)フランスに渡り、最初シャガールに、ついで初期ルネッサンスの画風にひかれ、
ルーベンスの大画面と肉感描写の迫力に魅了される。デ・キリコやエルンストの影響を受けて超現実主義の作品を描くようになる。
1931年(昭和6年) に帰国後、独立美術協会を舞台にシュルレアリスムの方法による大作を発表し続け、わが国の美術界に大きな衝撃と影響を与えた。
1941年(昭和16年) には、超現実主義者は共産主義者であるという戦時下のいわれなき嫌疑を受け、半年あまりの間、拘置される。
戦後「人間に執着し、人間を描く事に於いては、戦後の混乱期が、最も精彩があったように思う。」と自らが述べるように、モニュメンタルな人間群像を次々と発表する。
1949年(昭和24年) 美術文化協会を脱会する。
1950年(昭和25年) に北海道を旅して北海道風物を主題とした作品の発表を皮切りにヨーロッパはもとより、中南米、南アジア、ニューギニアなどの世界各地を巡って、人間の諸相をテーマに文明批評とも言える壮大なスケールの大作を次々と発表し続けた。
人間探求の制作欲はとどまるところを知らず、神話や地獄、さらには歴史をテーマに、絵画に思想と主題を盛り込むという希有な福沢美術を展開した。
1978年(昭和53年) 文化功労者に選ばれる。1991年(平成3年) 文化勲章受賞。
|
|
 |
 |
|