○伊勢崎市証明書コンビニ交付サービス管理運営規則
平成28年10月5日規則第79号
伊勢崎市証明書コンビニ交付サービス管理運営規則
(趣旨)
第1条 この規則は、個人番号カード又は移動端末設備を利用してコンビニエンスストア等に設置されている特定端末機により証明書を自動交付するサービス(以下「証明書コンビニ交付サービス」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔令和5年規則59号〕
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 個人番号カード 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。
(2) 特定端末機 地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して、本市の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された通信端末機器であって、証明書を交付する機能を有するものをいう。
(3) 個人番号カード用利用者証明用電子証明書 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書をいう。
(4) 暗証番号 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項又は第59条の3第2項の規定により設定された暗証番号をいう。
(5) 移動端末設備 公的個人認証法第16条の2第1項に規定する移動端末設備をいう。
(6) 移動端末設備用利用者証明用電子証明書 公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明電子証明書をいう。
一部改正〔令和5年規則59号〕
(利用者の範囲)
第3条 証明書コンビニ交付サービスを利用することができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者(以下「住民」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づき本市の戸籍に記載されている者(以下「本籍人」という。)であって、個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録された個人番号カード又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されている電磁的記録媒体が組み込まれている移動端末設備を所持しているものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、証明書コンビニ交付サービスを利用することができない。
(1) 満15歳未満の者
(2) 成年被後見人
(3) ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等及び児童虐待並びにこれらに準ずる行為の被害者支援に係る措置(以下「支援措置」という。)の対象者
(4) その他市長が適当でないと認める者
一部改正〔令和5年規則59号〕
(証明書の種類)
第4条 証明書コンビニ交付サービスの利用者(以下「利用者」という。)は、個人番号カード又は移動端末設備を利用して、自ら特定端末機で暗証番号の入力又はこれに代わる認証を行うとともに、必要な事項の入力及び選択をすることにより、市長に対し、次に掲げる証明書(以下「対象証明書」という。)の交付を請求することができる。
(1) 利用者又は利用者と同一の世帯に属する者に係る住民票の写し
(2) 利用者に係る印鑑登録証明書
(3) 利用者に係る所得証明書
(4) 利用者に係る所得課税証明書
(5) 利用者に係る戸籍の謄本又は利用者若しくは利用者と同一の戸籍に記載されている者に係る戸籍の抄本
(6) 利用者又は利用者と同一の戸籍に記載されている者に係る戸籍の附票の写し
2 市長は、地方公共団体情報システム機構が定める方法により、利用者が住民基本台帳法第7条第4号、第5号及び第8号の2に掲げる事項の記載について特定端末機で選択した場合は、同法第12条第5項に規定する特別の請求があったものとみなして、前項第1号の住民票の写しに当該事項の全部又は一部を記載することができる。
一部改正〔令和5年規則59号〕
(証明書コンビニ交付サービスにおける本人確認)
第5条 伊勢崎市戸籍事務及び住民基本台帳事務に係る本人確認取扱規則(平成26年伊勢崎市規則第79号。以下「本人確認規則」という。)第2条第3項の市長が別に定める方法は、利用者が個人番号カード又は移動端末設備を利用して特定端末機で暗証番号を入力し、又はこれに代わる認証を行い、公的個人認証法第38条第1項の規定により利用者証明検証者が利用者証明用電子証明書の有効性について確認することによるものとする。
一部改正〔令和5年規則59号〕
(証明書の交付)
第6条 市長は、前条の確認により第4条第1項の規定による請求が適正であると認めたときは、地方公共団体情報システム機構が定める方法により、特定端末機で当該請求に係る証明書を交付する。
2 第4条第1項の規定にかかわらず、市長は、支援措置の対象者が記載されている証明書を交付しない。
(戸籍証明書の利用登録)
第7条 本籍人(住民を除く。)は、第4条第1項第5号及び第6号に規定する証明書(以下「戸籍証明書」という。)の交付を請求しようとするときは、地方公共団体情報システム機構が定める方法により、あらかじめ市長に戸籍証明書の利用登録申請をしなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、当該申請があった日の翌日から起算して5日以内にその諾否を決定し、戸籍証明書の利用登録をするものとする。
3 前項の規定により戸籍証明書の利用登録をされた者(以下「本籍地証明利用者」という。)は、第4条第1項の規定により、証明書コンビニ交付サービスを利用して、市長に対し、戸籍証明書の交付を請求することができる。
4 前3項の規定は、本籍地証明利用者が個人番号カードの再交付を受けた場合その他個人番号カード用利用者証明用電子証明書又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書の記録事項に変更があった場合について準用する。
一部改正〔令和5年規則59号〕
(利用時間及び休止日)
第8条 証明書コンビニ交付サービスの利用時間は、午前6時30分から午後11時までとする。
2 証明書コンビニ交付サービスの休止日は、システムの保守点検日とする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、証明書コンビニ交付サービスの利用時間及び休止日を臨時に変更することができる。
一部改正〔令和元年規則32号〕
(手数料の納入等)
第9条 利用者は、対象証明書の交付を請求するに当たって、伊勢崎市手数料条例(平成17年伊勢崎市条例第80号。以下「手数料条例」という。)に定める手数料を特定端末機に入金するものとする。
2 前項の規定により既に納入した手数料は、還付しない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
3 手数料条例第7条の規定により第1項の手数料の不徴収又は免除を受けようとする者は、あらかじめ市長に申し出なければならない。
(利用変更申請)
第10条 利用者は、証明書コンビニ交付サービスの利用について、その全部又は一部を停止し、又は開始しようとするときは、証明書コンビニ交付サービス利用変更申請書(別記様式)により市長に申請しなければならない。この場合において、利用者は、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令(昭和60年自治省令第28号)第5条及び本人確認規則第3条に規定する書類を市長に提示し、又は提出しなければならない。
2 第3条第2項の規定にかかわらず、満15歳未満の者は、法定代理人の承諾がある場合に限り、前項の申請をすることにより証明書コンビニ交付サービスを利用することができる。この場合において、法定代理人は、戸籍の謄本その他その資格を証する書類として市長が適当と認めるもののほか、前項の規定の例により当該法定代理人に係る本人確認書類を市長に提示し、又は提出しなければならない。
(利用停止)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、証明書コンビニ交付サービスの利用について、その全部又は一部を停止するものとする。
(1) 個人番号カードの効力が失われたとき。
(2) 個人番号カード用利用者証明用電子証明書又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書の効力が失われたとき。
(3) 前条第1項の規定による申請があったとき。
(4) その他市長が必要と認めたとき。
一部改正〔令和5年規則59号〕
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、証明書コンビニ交付サービスの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成28年10月11日から施行する。
附 則(令和元年11月29日規則第32号)
この規則は、令和元年12月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第28号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月15日規則第59号)
この規則は、令和5年12月20日から施行する。
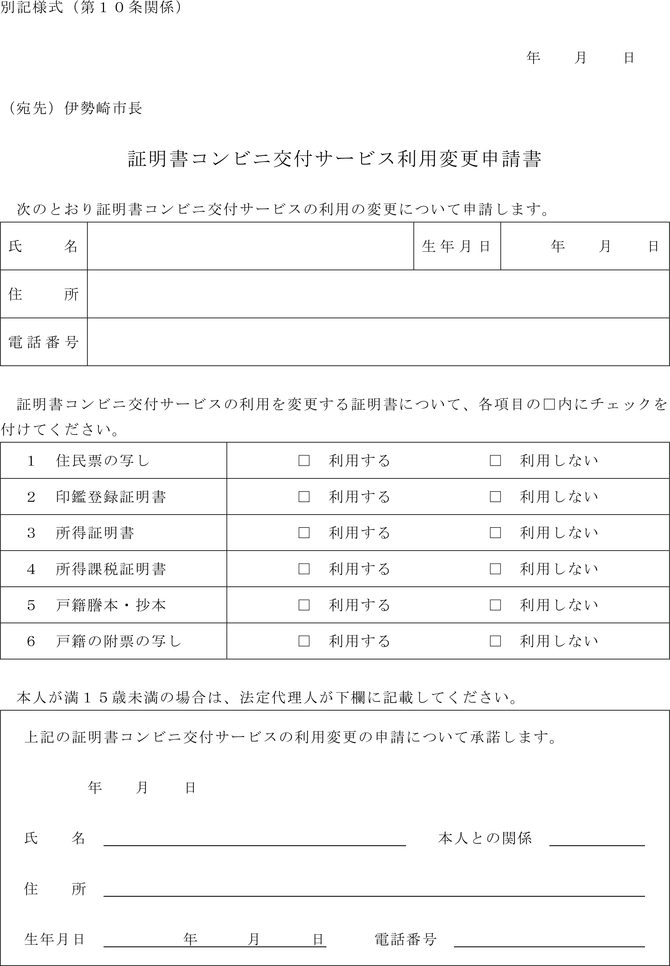
一部改正〔令和4年規則28号〕
