○伊勢崎市文書管理規程
平成17年1月1日訓令甲第11号
伊勢崎市文書管理規程
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 文書の受領、配布及び収受(第7条―第13条)
第3章 文書の作成(第14条―第19条)
第4章 文書の回議、合議、決裁及び供覧(第20条―第24条)
第5章 文書の浄書、施行等(第25条―第31条)
第6章 行政情報の整理、保管及び保存(第32条―第43条)
第7章 雑則(第44条・第45条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、伊勢崎市文書管理規則(平成21年伊勢崎市規則第17号。以下「規則」という。)第21条の規定に基づき、文書の取扱い並びに行政情報の整理、保管及び保存に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成21年訓令甲2号〕
(定義)
第2条 この訓令において使用する用語の意義は、規則で使用する用語の例によるもののほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 総合行政ネットワーク 地方公共団体を相互に接続する行政専用のネットワークであって、国の各府省庁を結ぶ府省庁間ネットワークと接続するネットワークをいう。
(2) 証明書 伊勢崎市電子署名規程(平成18年伊勢崎市訓令甲第4号)第2条第7号に規定する証明書をいう。
(3) 電子署名 伊勢崎市電子署名規程第2条第1号に規定する電子署名をいう。
(4) 保管文書 執務室内のファイリングキャビネット(以下「キャビネット」という。)において保管する行政情報をいう。
(5) 移換え キャビネットの上段及び中段に収納している行政情報(電子文書を除く。以下次号及び第7号において同じ。)のうち、その完結日の経過したものをキャビネットの下段に移すことをいう。
(6) 置換え キャビネットの下段に収納している保管期間の経過した行政情報を文書箱に入れて、規則第16条第2項に規定する書庫(以下「書庫」という。)に移すことをいう。
(7) 保存文書 書庫において保存する行政情報をいう。
一部改正〔平成18年訓令甲2号・4号・19年19号・21年2号・22年2号・24年4号・26年7号〕
(文書管理者の職務)
第3条 文書管理者(規則第5条第1項第1号に規定する文書管理者をいう。以下同じ。)は、課における文書事務を統括し、常に文書の管理の状況を把握し、その所掌する事務が適正かつ円滑に処理されるよう努めなければならない。
2 文書管理者は、毎年度初めに文書管理主任(規則第5条第1項第2号に規定する文書管理主任をいう。以下同じ。)及び文書管理担当者(規則第5条第1項第3号に規定する文書管理担当者をいう。以下同じ。)を指定し、その職及び氏名を文書担当課長に報告しなければならない。
3 文書管理者は、特別の理由により文書管理主任及び文書管理担当者を変更した場合は、速やかに文書担当課長に報告しなければならない。
追加〔平成21年訓令甲2号〕、一部改正〔平成22年訓令甲2号・23年5号〕
(文書管理主任の職務)
第4条 文書管理主任は、文書管理者の命を受け、課における適正な文書の管理に努め、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 文書の収受、配布及び発送に関すること。
(2) 文書の審査に関すること。
(3) 文書処理の促進及び改善に関すること。
(4) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び伊勢崎市情報公開条例(平成17年伊勢崎市条例第17号)に基づく保有個人情報の開示等又は行政情報の公開の請求の対象となる行政情報の特定に関すること。
(5) 電子文書の受信及び送信に関すること。
(6) 行政情報の分類基準の作成指導に関すること。
(7) 行政情報の移換え及び置換えの実地指導に関すること。
(8) 行政情報の整理、保管、保存及び廃棄の実地指導に関すること。
(9) 文書管理システムの運用指導に関すること。
(10) その他文書の管理に関し文書管理者が必要と認めること。
一部改正〔平成18年訓令甲2号・4号・21年2号・22年2号・24年4号・令和5年11号〕
(文書管理担当者の職務)
第5条 文書管理担当者は、課におけるファイリングシステムの維持管理及び電子文書の適正な管理に努め、文書管理主任の職務を補佐することのほか、次に掲げる職務を行う。
(1) 行政情報の分類基準の作成に関すること。
(2) 行政情報の移換え及び置換えに関すること。
(3) 行政情報の整理、保管、保存及び廃棄に関すること。
(4) 文書管理システムの運用に関すること。
追加〔平成21年訓令甲2号〕、一部改正〔平成22年訓令甲2号・24年4号〕
(文書管理担当者会議)
第6条 文書担当課長は、文書事務の連絡調整を図るため、文書管理主任及び文書管理担当者で組織する会議(以下「文書管理担当者会議」という。)を設置し、必要に応じて文書管理担当者会議を開催することができる。
2 文書担当課長は、文書管理主任及び文書管理担当者に対し、文書の適正管理並びに歴史資料等の収集、選別及び保存の促進のために必要な知識を付与するとともに、意識の向上を図るために必要な研修等を行うものとする。
一部改正〔平成21年訓令甲2号・22年2号〕
第2章 文書の受領、配布及び収受
(文書の受領)
第7条 本庁に郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)による発送(以下「郵送等」という。)、使送又はファクシミリにより到達した文書は、文書担当課において受領するものとする。
2 支所及び出先の部の庶務担当課(以下「出先機関」という。)に到達した文書は、当該出先機関において受領するものとする。
3 課に直接到達した文書及び会議等で直接配布された文書は、当該課において受領するものとする。
4 勤務時間外に到達した文書は、伊勢崎市役所当直服務規程(平成17年伊勢崎市訓令甲第20号)の規定により処理しなければならない。
5 郵送等に要する料金(以下「郵便料等」という。)の未払又は不足の文書が到達したときは、文書担当課長又は出先機関の長が認めるものに限り、未払又は不足の郵便料等を支払って受領することができる。
一部改正〔平成18年訓令甲2号・19年19号・22年2号・24年4号〕
(特殊文書の受領)
第8条 文書担当課又は出先機関(以下「文書担当課等」という。)は、前条の規定により、次に掲げる文書(以下「特殊文書」という。)を受領したときは、特殊文書処理票(様式第1号)に所要事項を記入するものとする。この場合において、文書担当課が受領したときにあっては文書担当課欄に、出先機関が受領したときにあっては庶務担当課欄に押印するものとする。
(1) 書留扱い(郵便法(昭和22年法律第165号)の規定による郵便物の特殊取扱をいう。以下同じ。)又は信書便の役務のうち書留扱いに準ずるものとして文書担当課長が定めるもの(以下「書留扱い等」という。)による文書
(2) 現金、有価証券等が同封されている文書
2 前項の規定により文書担当課等において受領した特殊文書及び所要事項を記入した特殊文書処理票(以下「特殊文書等」という。)は、主管の課別に仕分し、当該課の文書管理主任に配布するものとする。この場合において、特殊文書処理票の主管課欄に受領印を受けなければならない。
一部改正〔平成19年訓令甲10号・19号・22年2号・23年5号・24年4号〕
(文書の仕分及び配布)
第9条 文書担当課等において受領した文書は、次に掲げるところにより処理するものとする。
(1) 封入されている文書は、開封しないで仕分するものとする。ただし、課が判明しないものについては、開封して配布先を決定することができる。この場合において、文書担当課等が当該文書を開封したことを証するため、封筒の表に文書収受印(様式第2号)を押印しなければならない。
(2) 前号ただし書の規定により文書を開封した場合において、当該文書に現金又は有価証券、債権証書その他の権利を証する証書が添えられているときは、当該文書を特殊文書として取り扱わなければならない。ただし、諸証明類の請求に係るものは、この限りでない。
(3) 課が明らかでない文書又は2以上の課に関係のある文書は、最も関係のあると認める課に仕分するものとする。
2 本庁において仕分された文書は、特殊文書を除いて、部及び支所(以下「部等」という。)の庶務担当課が受領するものとする。
3 部等の庶務担当課は、前項の規定による文書を主管の課別に仕分し、当該課の文書管理主任に配布するものとする。
4 出先機関において仕分された文書及び前条の規定により出先機関が受領した特殊文書等は、主管の課の文書管理主任に配布するものとする。この場合において、当該文書が特殊文書であるときにあっては、特殊文書処理票の主管課欄に受領印を受けなければならない。
一部改正〔平成18年訓令甲2号・19年10号・20年3号・21年2号・22年2号・23年5号・24年4号〕
(文書の収受)
第10条 第7条第3項の規定により受領し、又は前条第3項及び第4項の規定により配布を受けた文書は、文書管理主任が当該文書の右下余白部分に文書収受印を押印し、収受発送簿(様式第3号)に所要事項を登録の上、文書収受印の所定欄に収受発送簿に登録した番号を記入し、収受するものとする。ただし、次の各号に掲げる文書については、当該各号に定める基準により処理することができる。
(1) カタログ、パンフレット、ポスター、定期刊行物類、挨拶状、案内状、権利の得喪変更に関係しない文書類、日報、月報等の報告書類、提出又は回答義務のない照会文書類、参考、速報として送付される法令等の制定改廃の通知文書類等で、供覧(第24条第1項に規定する供覧をいう。)にとどまる文書類は、文書収受印を押印し、収受発送簿の登録を省略することができる。
(2) 納入通知書、請求書、領収書類及び庁内文書等は、文書収受印及び収受発送簿の登録を省略することができる。
(3) 課の業務として提出される証明願、申告書、申請書、届書類、市民の声、苦情、陳情書類、身上調査、犯罪人通知等個人のプライバシーに関する文書類等で、課の日付印又は受付簿等で収受する文書は、収受事務の全部を省略し、別の手続によることができる。この場合において、課の日付印又は受付簿等は、文書管理者が文書担当課長と協議して定めるものとする。
2 前項の場合において、収受発送簿に登録すべき事項を文書管理システムに記録した電磁的記録をもって、当該収受発送簿に代えることができる。
3 文書管理主任は、前条第3項及び第4項の規定により特殊文書の配布を受けたときは、文書管理者に提示し、特殊文書処理票の主管課長欄に受領印を受けなければならない。
一部改正〔平成19年訓令甲10号・20年3号・21年2号・22年2号・24年4号・25年2号・26年7号〕
(文書の返付等)
第11条 課において受領し、又は配布を受けた文書のうち、その所管に属さない文書があるときは、次に定めるところにより転送し、又は返付しなければならない。
(1) 所管に属さない特殊文書は、直ちに文書担当課に返付する。
(2) 所管すべき課が明らかな文書は、直ちに主管の課に転送する。
(3) 所管すべき課が明らかでない文書は、直ちに文書担当課等に返付する。
2 課において受領し、又は配布を受けた文書のうち、封書(私信を除く。)を開封した場合において、当該文書に現金又は有価証券、債権証書その他の権利を証する証書が添えられているときは、当該文書を文書担当課等に返付するものとする。ただし、諸証明類の請求に係るものは、この限りでない。
一部改正〔平成19年訓令甲10号・22年2号・24年4号〕
(文書管理者の閲覧及び配布)
第12条 第10条第1項の規定により収受した文書は、文書管理主任が文書管理者の閲覧に供し、当該文書に係る事務を担当する係長(係長相当職を含む。以下同じ。)に配布するものとする。
2 前項に規定する場合において、文書管理者は、収受した文書と収受発送簿に登録した事項に相違がないことを確認するものとする。ただし、第10条第2項の規定により収受するものにあっては、文書管理システムに記録された事項を確認するものとする。
3 文書管理者は、特に必要と認められる文書は、文書管理主任又は係長に対して、その取扱い、処理等について必要な指示をするものとする。
一部改正〔平成21年訓令甲2号・24年4号・令和5年11号〕
(電子文書の収受等)
第13条 第7条から前条までの規定にかかわらず、収受等の処理(第7条から前条までの規定による文書の処理をいう。以下この条において同じ。)は、総合行政ネットワークその他の通信回線(以下「総合行政ネットワーク等」という。)を利用して行うことができる。
2 総合行政ネットワーク等に接続した電子計算機により受信した電子文書は、課において文書管理主任が次に掲げるところにより処理するものとする。
(1) 電子署名が付与された電子文書を受信した場合は、当該文書の電子署名を検証する。
(2) 受信した電子文書に形式上の誤りがないときは、当該文書の内容を速やかに出力して紙に記録し、到達した文書とみなす。
3 前項の場合において、証明書を利用するときは、伊勢崎市電子署名規程第8条第1項に規定する証明書利用者(以下「証明書利用者」という。)が処理するものとする。
4 前3項の規定により処理した文書の収受等の処理は、第7条から前条までの規定を準用する。この場合において、当該文書に電子署名が付与されているものにあっては、その旨を併せて登録するものとする。
5 第2項及び前項の規定にかかわらず、文書管理者が文書の性質、内容等により、軽易な取扱いができると認めた場合は、当該文書に係るこれらの処理を省略することができる。
追加〔平成18年訓令甲2号〕、一部改正〔平成18年訓令甲4号・21年2号・22年2号・24年4号・26年7号〕
第3章 文書の作成
(起案)
2 前項の起案は、起案用紙又は簡易起案用紙に記載すべき事項を文書管理システムに登録して行うものとする。
3 文書担当課長は、前2項の規定にかかわらず、事務の効率的処理を目的として、決裁処理印(様式第6号)又は課の所管する事務の処理の態様に応じた用紙を用いて起案させることができる。
一部改正〔平成21年訓令甲2号・22年2号・23年5号・24年4号〕
(起案の要領)
第15条 起案は、次に掲げる事項に留意して行うものとする。
(1) 原則として、1事案ごとに行うこと。この場合において、関連する事案については、一括して処理することができる。
(2) 決裁権者が一読して起案内容を把握できるよう起案文書の概要を起案用紙に簡潔に記載すること。
(3) 根拠法令等その他の参考資料は、要点を抜き書き又は複写をして添えること。
(4) 経費を伴う事案については、予算との関係を明らかにすること。
(5) 同一の事案で、起案を重ねる場合は、その完結に至るまでの関係書類を添付すること。
(6) 施行する文書(以下「施行文書」という。)の期日が予定された事案については、決裁を受けるための時間的な余裕をもって起案すること。
2 起案用紙は、起案者が次に掲げるところにより、記入するものとする。
(1) 決裁欄は、決裁権者(伊勢崎市事務専決規程(令和5年伊勢崎市訓令甲第3号)第2条第8号に規定する決裁責任者又は同条第9号に規定する専決権者をいう。以下同じ。)より上位欄に「斜線」又は「*」を表示すること。伊勢崎市事務専決規程第5条第3項の規定が適用される者の決裁欄についても、同様とする。
(2) 起案者欄は、起案者の所属、職、氏名及び内線又は電話を記入し、氏名の末尾に認印を押印すること。
(3) 合議欄は、原則として、関係部課等の係長以上の職を、余白左上部から縦に職階順かつ横に所属建制順に記入すること。
(4) 文書番号欄は、収受発送簿への登録を要する文書について、次に掲げるところにより、収受発送簿に登録した番号を記入すること。
ア 第10条第1項(第13条第4項において準用する場合を含む。)の規定により収受した文書は、収受発送簿に登録した番号を記入すること。
イ 第26条第2項の規定により収受発送簿に登録を要する文書は、決裁権者の決裁を受けた後、収受発送簿に必要事項を登録の上、当該登録した番号を記入すること。
(5) 起案日欄は、起案文書の作成を終了した年月日を記入すること。
(6) 施行日欄は、決裁権者の決裁を受けた後、発送、公告その他文書を施行した年月日を記入すること。
(7) 保存期間欄は、規則第10条第1項本文の規定により定めた保存期間を記入すること。ただし、規則第10条第1項ただし書の規定により保存期間を定めない行政情報については、次に掲げるところにより処理すること。
ア 文書管理者が常時利用する必要があると認めるものについては、常用と記入すること。
イ 一時的かつ補助的な用途に用いるものについては、随時と記入すること。
ウ 起案日と同一年度内に完結しない事務又は事業に係るものについては、継続と記入すること。
(8) 情報公開欄は、次に掲げるところにより処理し、伊勢崎市情報公開条例第7条第1項各号に規定する非公開情報の該当性について第1次判断を行うこと。
ア 公開等の区分欄は、該当するものを■と記入すること。
イ 非公開理由欄は、該当するものを■と記入すること。
(9) 個人情報欄は、該当するものを■と記入すること。
(10) 公印押印欄は、該当するものを■と記入すること。
(11) 文書分類欄は、収納する個別フォルダーの名称を記入すること。
(12) 施行・取扱上の注意(意見)欄は、必要に応じて重要、至急、議案、秘密等を表示し、文書の適確な処理を図ること。
(13) 宛先欄は、宛先の名称を記入すること。
(14) 発信者欄は、該当するものを■と記入すること。
(15) 施行文書の発送方法欄は、該当するものを■と記入すること。
(16) 件名欄は、事案の題名、件名等を要領よく簡潔に記入すること。
(17) 伺文欄は、起案内容の結論部分を簡潔に記入すること。
(18) 内容欄は、起案文書の概要、起案の理由及び経過、参考事項等を箇条書で簡潔に記載すること。
一部改正〔平成18年訓令甲2号・19年10号・19号・20年3号・21年2号・22年2号・23年5号・24年4号・25年2号・26年7号・29年1号・令和5年11号〕
(書式)
第16条 文書の書式は、左横書きとする。ただし、次に掲げるものは、縦書きとする。
(1) 法令等の規定により縦書きと定められているもの
(2) 賞状、表彰状、感謝状、祝辞、弔辞その他の文書であって、市長が縦書きを必要と認めたもの
一部改正〔平成24年訓令甲4号・31年1号〕
(文書作成の原則)
第17条 文書は、伊勢崎市公文例規程(平成17年伊勢崎市訓令甲第12号。以下「公文例規程」という。)に定めるところにより、平易かつ簡明な表現を用いて作成しなければならない。
一部改正〔平成19年訓令甲19号・21年2号・22年9号・24年4号〕
(文書の記号及び番号)
第18条 施行文書には、次に掲げるところにより、文書の記号及び番号を付さなければならない。
(2) 公文例規程第2条に規定する指令及び達(以下「指令等」という。)については、市名、指令等の種別名、別表第1に定める文書の記号(以下「文書記号」という。)及び第3項に規定する令達番号を付すること。
(3) その他通知、照会、回答等の文書(以下この条において「回答の文書等」という。)については、文書記号に市名の首字を冠し、第4項及び第5項に規定する文書番号を付すること。
2 前項の規定にかかわらず、回答の文書等のうち、次に掲げるものには、文書の記号及び番号を付さないことができる。
(1) 権利、義務等に関係のない簡易な対外文書
(2) 部課等の相互間で発する庁内文書
(3) 挨拶、書簡の類
(4) 定例的で簡易な通知、報告の類
(5) 刊行物、資料等の送付書の類
(6) その他文書管理者が回答の文書等の性質、内容等により文書の記号及び番号を付す必要がないと認めたもの
3 条例等については法規担当課が例規番号簿(様式第7号)を、指令等については課が令達番号簿(様式第8号)を備えて、次に掲げるところにより令達番号を定め、所要事項を記入しなければならない。この場合において、例規番号簿及び令達番号簿に記入すべき事項を文書管理システムに記録した電磁的記録をもって、当該例規番号簿及び令達番号簿に代えることができる。
(1) 条例等の令達番号は、暦年ごとにこれを更新すること。
(2) 指令等の令達番号は、年度ごとにこれを更新すること。
4 回答の文書等については、課が収受発送簿を備えて、文書番号は年度ごとにこれを更新するものとする。収受発送簿に登録すべき事項を文書管理システムに記録する場合においても、同様とする。
5 前項の規定による文書番号は、文書の収受発送の一連番号とする。この場合において、同一事案に属する往復文書は、完結するまで同一の文書番号に枝番号を2から付するものとする。
一部改正〔平成20年訓令甲3号・21年2号・22年2号・23年5号・24年4号・26年7号・31年1号・令和3年4号〕
(施行者名等)
第19条 施行文案の施行者名は、市長とする。ただし、当該文書の性質及び内容により、副市長、部長(会計管理者を含む。以下同じ。)、副部長(支所長を含む。以下同じ。)若しくは課長の職又は市名、部等、課若しくは施設の名称を用いることができる。
2 前項の規定により職を用いる場合においては、職のほかに当該職にある者の氏名を併せて用いるものとする。
3 前2項の規定による施行者名のほか、施行文案には、受信者の便宜のため、必要に応じて課の名称及び電話、内線等を記載するものとする。
一部改正〔平成19年訓令甲10号・21年2号・22年2号・24年4号・28年5号・令和6年5号〕
第4章 文書の回議、合議、決裁及び供覧
(回議及び合議)
第20条 起案文書は、伊勢崎市事務専決規程第5条の規定により回議又は合議を経て、決裁権者の決裁を受けるものとする。
2 起案文書を合議する場合において、事前に意見を調整した上で起案したときは、合議を省略することができる。
3 合議の順序は、次に掲げるところにより、決裁権者の意思決定の前に行うものとする。
(1) 同一の部等内の他の課の事務に関係のある起案文書は、主管の課長の回議を経てから同一の部等内の他の課に合議する。ただし、主管の課長が専決するときは、主管の課長補佐の回議を経てから同一の部等内の他の課に合議する。
(2) 他の部等又は課の事務に関係のある起案文書は、次に掲げる決裁権者の区分に応じ、それぞれ定める順序により当該起案文書を回付する。
ア 市長又は副市長 主管の部長の回議を経てから他の部等又は課に合議する。
イ 部長又は副部長 主管の課長の回議を経てから他の部等又は課に合議する。
ウ 課長 主管の課長補佐の回議を経てから他の部等の課に合議する。
4 起案文書の回議を受けた職員は、当該起案文書の所定欄に専決印又は認印を押印するものとする。
5 起案文書の合議を受けた職員は、当該起案文書の所定欄に認印を押印するものとする。
6 起案文書の回議又は合議を受けた職員は、当該起案文書を修正したときは、修正箇所に認印を押印するものとする。ただし、修正することによって起案の趣旨に変更が及ぶものは、起案者又は主管の課長と協議しなければならない。
7 起案文書の合議を受けた部長、副部長又は課長は、当該起案文書に重大な異議を認めたときは、当該起案文書に係る事務を所管する主管の部長、副部長又は課長と協議するものとする。この場合において、協議が整わないときは、当該起案文書にその旨を表示し、意見を付し、上司の指揮を受けるものとする。
8 起案者は、前2項の規定により当該起案文書に重要な修正が行われる等その内容に著しい変更があったとき、又は起案文書を取り下げたときは、回議又は合議をした関係者に対して、その旨を通知し、又は再度回議若しくは合議をしなければならない。
一部改正〔平成19年訓令甲10号・19号・21年2号・22年2号・24年4号・25年2号・29年1号・令和5年11号〕
(重要な起案文書等の取扱い)
第21条 重要かつ即決を要する起案文書又は特別な理由がある起案文書は、起案者又はその上位の職にある者が当該文書を携帯して、その要旨を説明し、回議又は合議をするものとする。
2 秘密を要する起案文書は、封筒に入れ、文書管理者が自ら携帯して、回議又は合議をするものとする。
一部改正〔平成21年訓令甲2号・24年4号〕
(文書管理主任の文書審査)
第22条 起案文書は、文書管理主任の審査を受けるものとする。
2 文書管理主任は、前項に規定する審査に当たっては、次に掲げる事項に適合するよう、起案文書の修正又は事務担当者に対して必要な指示をすることができる。
(1) 起案の形式
(2) 所要事項の記載
(3) 文書の書式
(4) 公用文の作成基準
(5) 文書の記号及び番号
(6) 施行者名
(7) 参考資料
一部改正〔平成21年訓令甲2号・24年4号〕
(法規審査)
第23条 次に掲げる起案文書は、法規審査を受けなければならない。
(1) 条例及び規則に係るもの
(2) 告示、公告、訓令等に係るもの
(3) 法令の解釈及び運用に係るもので重要なもの
(4) 行政事件訴訟、民事訴訟、不服申立て等に係るもので重要なもの
一部改正〔平成21年訓令甲2号・24年4号〕
(供覧)
第24条 第12条(第13条第4項において準用する場合を含む。)の規定により配布を受けた文書又は事務担当者が起案以外の事務に関して作成した文書で、当該文書に係る事務に関係のある者の閲覧に供すること(以下「供覧」という。)によって完結するものは、供覧用紙(様式第9号)により供覧するものとする。
2 前項の供覧は、供覧用紙に記載すべき事項を文書管理システムに登録して行うものとする。
一部改正〔平成19年訓令甲19号・21年2号・23年5号・24年4号〕
第5章 文書の浄書、施行等
(文書の浄書及び照合)
第25条 施行文書の浄書は、課において行うものとする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
2 前項の規定による浄書が終わったときは、課において浄書した施行文書と決裁を受けた施行文案とを照合しなければならない。
一部改正〔平成21年訓令甲2号・22年2号・24年4号〕
(収受発送簿への登録)
第26条 第10条第1項本文の規定により収受した文書に基づく施行文書は、当該収受した文書に係る収受発送簿に所要事項を登録しなければならない。
2 前項に規定するもの以外の施行文書であって、文書管理主任が施行、処理経過等を記入する必要があると認めるものは、収受発送簿に所要事項を登録しなければならない。
3 前2項の場合において、収受発送簿に登録すべき事項を文書管理システムに記録した電磁的記録をもって、当該収受発送簿に代えることができる。
一部改正〔平成18年訓令甲2号・21年2号・23年5号・24年4号〕
(公印の押印)
第27条 施行文書には、伊勢崎市公印規程(平成17年伊勢崎市訓令甲第14号)に規定する公印を押印するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる施行文書には、公印の押印を省略することができる。この場合において、当該施行文書中に公印省略と括弧書きするものとする。
(1) 権利、義務等に関係のない簡易な対外文書
(2) 部課等の相互間で発する庁内文書
(3) 挨拶、書簡の類
(4) 定例的で簡易な通知、報告の類
(5) 刊行物、資料等の送付書の類
(6) その他文書管理者が施行文書の性質、内容等により公印の押印を要しないと認めたもの
3 公印を押印した施行文書のうち、権利、義務等に関するものその他文書管理者が必要と認めたものには、決裁を受けた施行文案と契印をもって割印するものとする。
一部改正〔平成21年訓令甲2号・22年2号・24年4号・31年1号〕
(電子署名)
第28条 前条の規定にかかわらず、施行する電子文書(送信するものに限る。以下同じ。)については、伊勢崎市電子署名規程に規定するところにより、電子署名を付与するものとする。ただし、当該施行する電子文書が前条第2項各号のいずれかに該当する場合にあっては、この限りでない。
追加〔平成18年訓令甲2号〕、一部改正〔平成18年訓令甲4号・21年2号・24年4号〕
(施行文書の発送)
第29条 施行文書の発送は、郵送等又は使送により、文書担当課が行うものとする。
2 前項に規定する郵送等による施行文書(以下「郵送等文書」という。)は、課において封筒に入れ、又は包装して宛先を明記するとともに、書留、速達その他の書留扱い等を要するものにあってはその旨を表示し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより文書担当課長に郵送等の依頼をするものとする。この場合において、文書担当課長への依頼は、急を要する場合及び年末年始を除き、当日の午後2時までに行うものとする。
(1) 郵送する場合 郵送等文書を入れた封筒等の表に料金後納の印を押印し、文書管理システムに所要事項を登録の上、郵便物等依頼票(様式第10号)を添え、文書担当課へ提出する。
(2) 信書便により発送する場合 郵送等文書に郵便物等依頼票を添え、文書担当課へ提出する。
3 前項の規定により提出された郵送等文書は、文書担当課において取りまとめ、郵送の場合にあっては文書管理システムにより料金後納郵便物差出依頼票(様式第11号)及び料金後納郵便物差出票(様式第12号)を作成し、日本郵便株式会社の事業所に、信書便による発送の場合にあっては施行文書の送達を引き受ける者に、それぞれ指定された手続により差し出すものとする。
4 前3項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、課において施行文書を発送することができる。この場合において、発送の手続は、当該課において前2項の規定の例により行うものとする。
(1) 急を要する場合
(2) 同時に多量の施行文書を発送する場合
(3) 出先機関において発送する場合
(4) その他文書担当課長が課において発送することが適当と認めるものを発送する場合
5 文書担当課長は、毎月初めに、各課の前月分の郵便料等について、伊勢崎市財務規則(平成17年伊勢崎市規則第43号)に規定する仕訳書を作成し、各課長に送付するものとする。
6 前項の規定により、仕訳書の送付を受けた課長は、毎月指定された期日までに郵便料等を支払わなければならない。
7 第4項に規定するもののほか、第2項及び第3項に規定する手続により郵送等をすることができない場合又は勤務時間外に郵送等をせざるを得ない場合は、文書担当課に備付けの郵便切手類、はがき等を文書担当課長が定める方法により請求し、これを使用して、課において施行文書を発送することができる。この場合において、文書担当課長は、郵便切手類等受払簿(様式第13号)により、郵便切手類、はがき等の受払いの状況を管理しなければならない。
一部改正〔平成19年訓令甲10号・19号・20年3号・21年2号・22年2号・23年5号・24年4号・14号〕
(県庁に送付する施行文書の取扱い)
第30条 群馬県庁に送付する施行文書は、前日の午後5時までに文書担当課の文書区分棚に搬入する。
一部改正〔平成21年訓令甲2号・24年4号〕
(電子文書の浄書、照合及び発送)
第31条 第25条及び第29条の規定にかかわらず、施行する電子文書に係る浄書、照合及び発送の処理は、総合行政ネットワーク等に接続した電子計算機を利用して行うことができる。この場合において、通信回線(総合行政ネットワークを除く。)に接続した電子計算機を利用してこれらの処理を行うことができる電子文書については、次に掲げるものに限る。
(1) 第27条第2項の規定により公印の押印及び契印の割印を省略することができるもの
(2) その他文書管理者が認めたもの
2 前項本文に規定する場合において、次の各号に掲げる電子計算機を利用した処理は、当該各号に掲げる処理とみなす。
(1) 決裁を受けた施行文案の浄書に係る事項の電子計算機への入力又は電子計算機により送信する電子文書の作成 浄書
(2) 電子計算機に入力した事項(以下「入力事項」という。)又は作成した電子文書と決裁を受けた施行文案との確認 照合
(3) 前号の確認を行った入力事項又は電子文書の電子計算機からの送信 発送
3 施行する電子文書の発送は、別に定めるところにより文書担当課又は課において文書管理主任が行うものとする。この場合において、文書担当課において発送するものにあっては、総合行政ネットワーク文書等件名簿(様式第14号)に所要事項を登録の上、行うものとする。
4 前項の場合において、証明書を利用するときは、証明書利用者が行うものとする。
追加〔平成18年訓令甲2号〕、一部改正〔平成18年訓令甲4号・21年2号・22年2号・24年4号〕
第6章 行政情報の整理、保管及び保存
追加〔平成21年訓令甲2号〕
(行政情報の分類基準及び目録の整備)
第32条 文書管理者は、規則第12条第1項の規定により定めた行政情報の分類基準に基づき、行政情報(保存期間が1年未満であるもの及び電磁的記録を除く。以下この条から第40条までにおいて同じ。)が適切に保管されているかについて、定期的に点検しなければならない。
(1) 行政情報の分類
(2) 個別フォルダーの名称
(3) 発生年度
(4) 保存期間
(5) 廃棄予定日
(6) その他文書担当課長が必要と認める事項
3 前項に規定する事項の登録は、次に掲げるときに行うものとする。
(1) 起案文書については、決裁の終了したとき。
(2) 供覧文書については、供覧の終了したとき。
(3) 前2号に掲げるもの以外の文書については、決裁又は供覧に準ずる手続が終了したとき。
4 文書管理者は、前年度に整備した行政情報の目録をもとに、毎年度初めに当該年度における行政情報の目録を作成するものとし、文書管理システムに登録されている事項に追加及び変更があったときは、その都度修正するものとする。この場合において、行政情報の分類基準の追加、変更及び削除は、文書担当課長が定める方法により、文書管理者が文書担当課長に申請することにより行うものとする。
追加〔平成21年訓令甲2号〕、一部改正〔平成22年訓令甲2号・24年4号〕
(行政情報の整理及び保管の方法)
第33条 規則第15条第1項第2号に規定する別に定める行政情報の保管用具は、キャビネット及び次に掲げるファイル用品とする。
(1) 第1ガイド及び第2ガイド
(2) 個別フォルダー
(3) ガイドラベル及び個別フォルダーラベル
(4) その他ファイリングシステムの実施に必要な用品
2 行政情報は、原則として、規則第12条第1項の規定により定めた行政情報の分類基準ごとに分類及び整理をした上で個別フォルダーに収納するものとする。この場合において、1の行政情報が複数の分類基準に該当するときは、最も関係の深い分類基準により当該行政情報の分類及び整理をするものとする。
3 前項の分類及び整理について、複数の行政情報が相互に関係があり、同一の分類基準として分類及び整理をすることが適当な場合において、行政情報の保存期間が同一でないときは、最も長い保存期間の分類基準として、当該行政情報の分類及び整理をするものとする。
4 規則第10条第1項各号に規定する行政情報にあっては、次の各号に掲げる区分により、当該各号に定める旨を個別フォルダーラベルに表示するものとする。
(1) 文書管理者が常時利用する必要があると認める行政情報 常用文書
(2) 一時的かつ補助的な用途に用いる行政情報 随時保管文書
(3) 未完結の事務事業に係る行政情報 継続保管文書
5 キャビネットによる保管が不適当な行政情報は、別の保管庫(執務室内の戸棚、ロッカー等をいう。)に保管することができる。キャビネットを利用することができない場合においても、同様とする。
6 保管文書は、いかなる理由があっても抜き取り、差し替え、改ざんし、若しくは添削し、又は他に転貸してはならない。
追加〔平成21年訓令甲2号〕、一部改正〔平成22年訓令甲2号・24年4号・26年7号〕
(移換え)
第34条 保管文書の移換えは、毎年度初めに行うものとする。ただし、規則第10条第1項各号に規定する行政情報にあっては、文書管理者が職務の遂行上必要と認める期間、移換えを行わないことができる。
追加〔平成21年訓令甲2号〕、一部改正〔平成22年訓令甲2号・24年4号〕
(置換え)
第35条 保管文書の置換えは、毎年度の切替時に行うものとする。
2 前項に規定する置換えに係る保管文書は、保存期間別に文書箱に整理するものとする。
追加〔平成21年訓令甲2号〕、一部改正〔平成22年訓令甲2号・24年4号〕
(引継ぎ)
第36条 文書管理者は、前条第2項の規定により整理した文書箱を保管期間の経過した日の属する年度の翌年度の6月末日までに文書担当課長に引き継がなければならない。この場合において、文書箱の表面に次に掲げる事項を表示するものとする。
(1) 発生年度
(2) 保存期間
(3) 文書箱整理番号
2 文書担当課長は、前項の規定により引継ぎを受けた場合は、速やかに文書管理システムに所要事項を登録するものとする。
追加〔平成21年訓令甲2号〕、一部改正〔平成24年訓令甲4号〕
(書庫の管理)
第37条 書庫の利用は、勤務時間内とする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
追加〔平成21年訓令甲2号〕、一部改正〔平成22年訓令甲2号・24年4号〕
(保存文書の閲覧・借用)
第38条 保存文書を閲覧し、又は借用しようとするときは、保存文書閲覧・借用申請書(様式第15号)に必要事項を記入し、文書担当課長に申請するものとする。
2 保存文書の借用期間は、7日以内とする。ただし、文書担当課長が必要と認める場合は、この限りでない。
3 閲覧又は借用をした保存文書は、必ず元の位置に返しておかなければならない。
4 保存文書は、いかなる理由があっても抜き取り、差し替え、改ざんし、若しくは添削し、又は他に転貸してはならない。
追加〔平成21年訓令甲2号〕、一部改正〔平成22年訓令甲2号・23年5号・24年4号〕
(保存期間の延長)
第39条 文書管理者は、保存文書の保存期間を延長しようとするときは、文書担当課長の承認を得た上で、文書管理システムにより必要な措置を講じなければならない。
追加〔平成21年訓令甲2号〕、一部改正〔平成22年訓令甲2号・24年4号〕
(マイクロフィルムによる保存)
第40条 行政情報は、マイクロフィルムに撮影し、保存することができる。
2 マイクロフィルムの作成及び取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
追加〔平成21年訓令甲2号〕、一部改正〔平成24年訓令甲4号〕
(電磁的記録の保存等)
第41条 電磁的記録は、その種別、情報化の進展状況等を勘案して、文書管理者が適切な方法により管理するものとする。この場合において、文書管理者は、電磁的記録の改ざん、盗難、漏えい等を防止するために必要な措置を講じなければならない。
追加〔平成21年訓令甲2号〕、一部改正〔平成24年訓令甲4号〕
(保存文書等の廃棄)
第42条 文書担当課長は、規則第18条第1項の規定により文書管理者が廃棄の決定をした行政情報を裁断、溶解、焼却、消去その他適切な方法により処理しなければならない。
2 文書管理者は、規則第18条第4項の規定により行政情報を廃棄する場合は、前項の規定の例により処理しなければならない。
追加〔平成21年訓令甲2号〕、一部改正〔平成22年訓令甲2号・24年4号〕
(歴史資料等の選別及び保存の方法)
第43条 文書管理者は、規則第19条第1項に規定する歴史資料等の選別を保存期間の満了する前のできる限り早い時期に行うものとする。
2 文書管理者は、前項の規定により歴史資料等の選別を行ったときは、その保存期間を永年として定め、文書管理システムに所要事項を登録するものとする。
3 文書担当課長は、前項の規定による歴史資料等の選別を適正に行うため、教育委員会の協力を得て、別表第2に掲げる区分により、歴史資料等として選別する行政情報を別に定めなければならない。
追加〔平成22年訓令甲2号〕、一部改正〔平成24年訓令甲4号〕
第7章 雑則
一部改正〔平成21年訓令甲2号〕
(文書の管理の特例)
第44条 文書管理者は、文書の管理について、この訓令に定めるところと異なる取扱いをしようとするときは、文書担当課長の承認を得て、この訓令以外の方法により処理することができる。
追加〔平成21年訓令甲2号〕、一部改正〔平成24年訓令甲4号〕
(その他)
第45条 この訓令に定めるもののほか、文書の取扱い並びに行政情報の整理、保管及び保存に関し必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成21年訓令甲2号・24年4号〕
附 則
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日訓令甲第2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月25日訓令甲第4号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年1月4日から施行する。
附 則(平成19年3月28日訓令甲第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日訓令甲第19号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日訓令甲第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日訓令甲第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
(伊勢崎市文書整理、保管及び保存に関する規程の廃止)
2 伊勢崎市文書整理、保管及び保存に関する規程(平成17年伊勢崎市訓令甲第13号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この訓令の施行の日の前日までに廃止前の伊勢崎市文書整理、保管及び保存に関する規程(平成17年伊勢崎市訓令甲第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成22年3月30日訓令甲第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月30日訓令甲第9号)
この訓令は、平成22年11月30日から施行する。
附 則(平成23年3月30日訓令甲第5号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日訓令甲第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月24日訓令甲第14号)
この訓令は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日訓令甲第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日訓令甲第7号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成27年3月31日訓令甲第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日訓令甲第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月23日訓令甲第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成30年3月28日訓令甲第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月12日訓令甲第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日訓令甲第10号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日訓令甲第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日訓令甲第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月27日訓令甲第11号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日訓令甲第5号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第18条関係)
文書の記号
課の名称 | 文書の記号 |
秘書課 | 秘 |
総務課 | 総 |
行政課 | 行 |
管財課 | 管 |
職員課 | 職 |
安心安全課 | 安 |
企画調整課 | 企 |
事務管理課 | 事務 |
情報政策課 | 情 |
広報課 | 広 |
財政課 | 財 |
契約検査課 | 契 |
市民税課 | 市税 |
資産税課 | 資 |
収納課 | 収 |
市民課 | 市 |
市民活動課 | 市活 |
人権課 | 人 |
国際課 | 国 |
赤堀支所庶務課 | 赤庶 |
赤堀支所市民サービス課 | 赤市サ |
あずま支所庶務課 | あ庶 |
あずま支所市民サービス課 | あ市サ |
境支所庶務課 | 境庶 |
境支所市民サービス課 | 境市サ |
環境政策課 | 環 |
GX推進課 | GX |
資源循環課 | 資循 |
清掃リサイクルセンター21 | 清 |
国民健康保険課 | 国保 |
年金医療課 | 年 |
健康づくり課 | 健 |
スポーツ振興課 | ス |
社会福祉課 | 社 |
子育て支援課 | 子 |
こども保育課 | こ保 |
障害福祉課 | 障 |
高齢政策課 | 高 |
介護保険課 | 介 |
指導監査課 | 指 |
商工労働課 | 商 |
企業誘致課 | 企誘 |
文化観光課 | 文 |
農政課 | 農 |
農村整備課 | 農整 |
道路整備課 | 道整 |
道路管理課 | 道管 |
治水課 | 治 |
住宅課 | 住 |
建築課 | 建 |
都市計画課 | 都 |
交通政策課 | 交 |
建築指導課 | 建指 |
公園緑地課 | 公 |
区画整理課 | 区 |
事業課 | 事 |
会計課 | 会 |
一部改正〔平成18年訓令甲2号・19年10号・19号・20年3号・21年2号・22年2号・23年5号・24年4号・25年2号・27年1号・28年5号・30年2号・令和2年10号・3年4号・4年3号・6年5号〕
別表第2(第43条関係)
歴史資料等の区分
(1) 条例、規則、訓令、通達等の例規に関するもの
(2) 市の各種制度及び行政組織の新設並びに改廃に関するもの
(3) 市町村の廃置分合等に関するもの
(4) 地方自治制度に関するもの
(5) 選挙に関するもの
(6) 議会、行政委員会、附属機関(附属機関に準ずるものを含む。以下同じ。)、主要会議等の審議経過及び結果に関するもの
(7) 諮問及び答申に関するもの
(8) 調査、統計等に関するもの
(9) 予算、決算及び収支その他財政状況に関するもの
(10) 起債及び補助金に関するもの
(11) 市有財産の取得、管理及び処分に関するもの
(12) 許可、認可、承認等に関するもの
(13) 監査、検査等に関するもの
(14) 行政委員会及び附属機関の委員の人事に関するもの
(15) 叙位、叙勲、褒章、表彰等に関するもの
(16) 訴訟、和解及び不服申立てに関するもの
(17) 陳情、請願、要望等に関するもの
(18) 市の総合計画その他の市の重要な基本計画に関するもの
(19) 市有財産及び公の施設の設置等に関するもの
(20) 各種施策、行政運営上のシステム等の事業の実施に関するもの
(21) 市内の史跡、文化財等に関するもの
(22) 外国及び外国人に関するもの
(23) 儀式、行事その他市内で起きた及び市に関わりのあった大きな出来事に関するもの
(24) その他重要と思われるもの
追加〔平成22年訓令甲2号〕、一部改正〔平成24年訓令甲4号〕
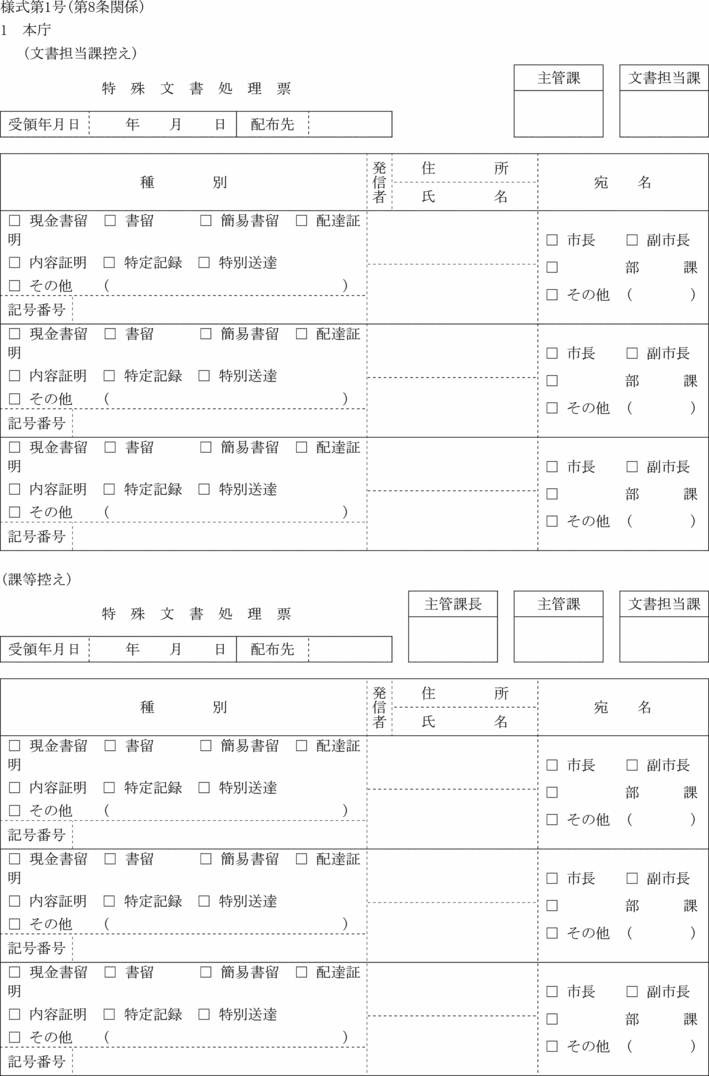
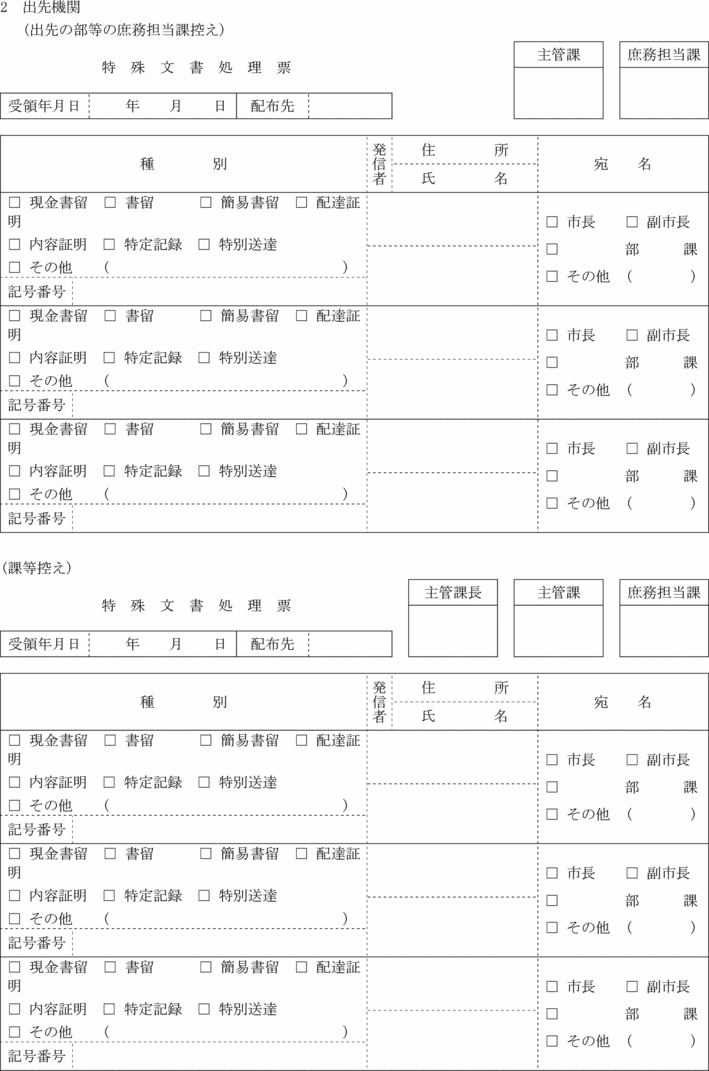
全部改正〔平成24年訓令甲4号〕
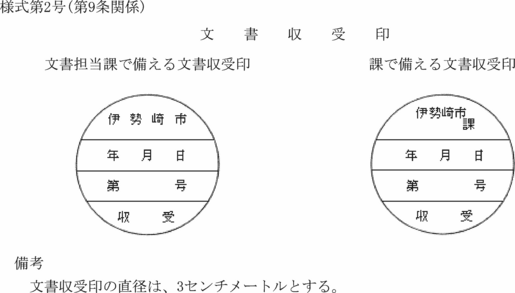
一部改正〔平成22年訓令甲2号・24年4号・25年2号〕
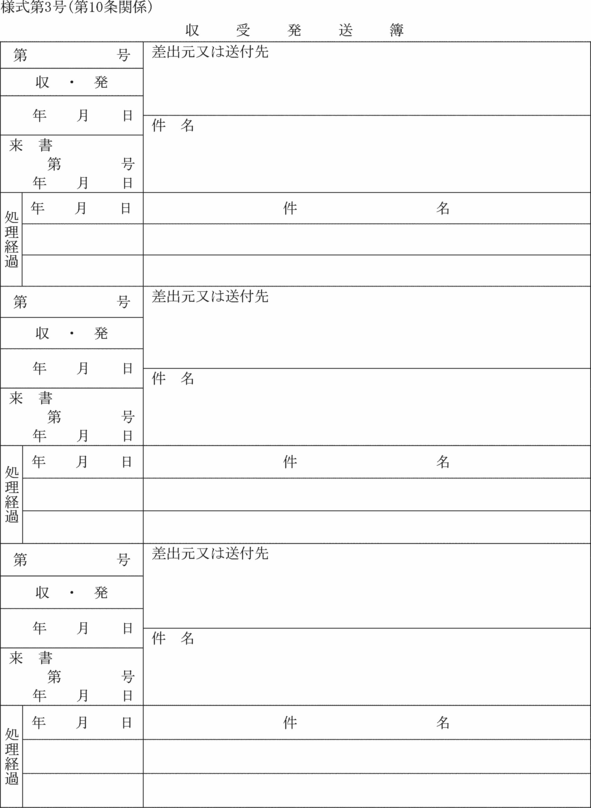
一部改正〔平成24年訓令甲4号〕
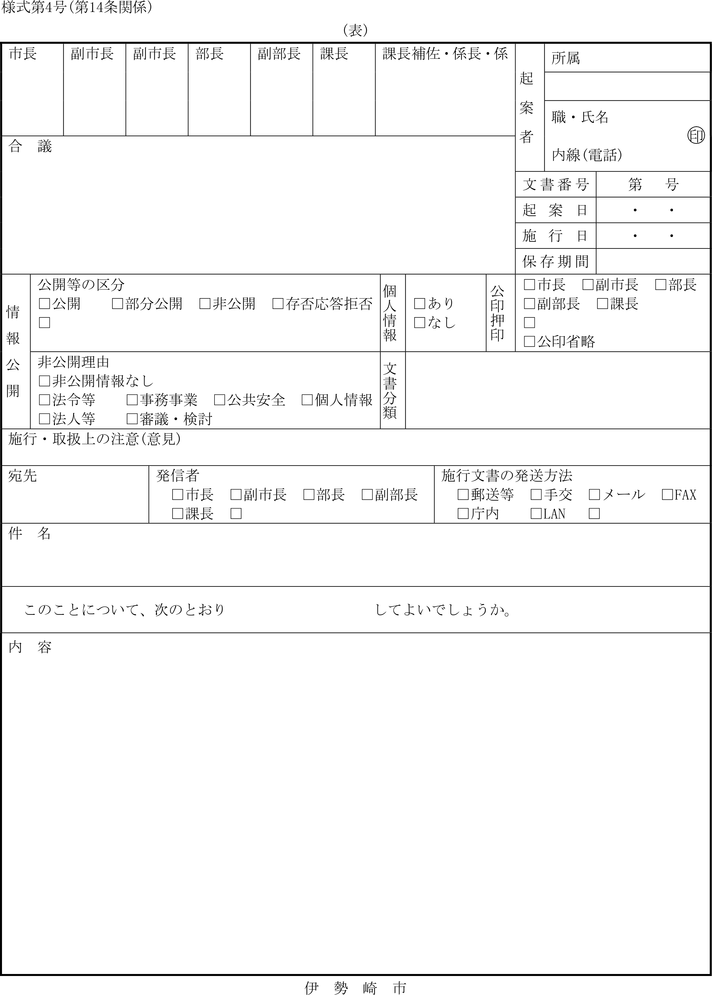
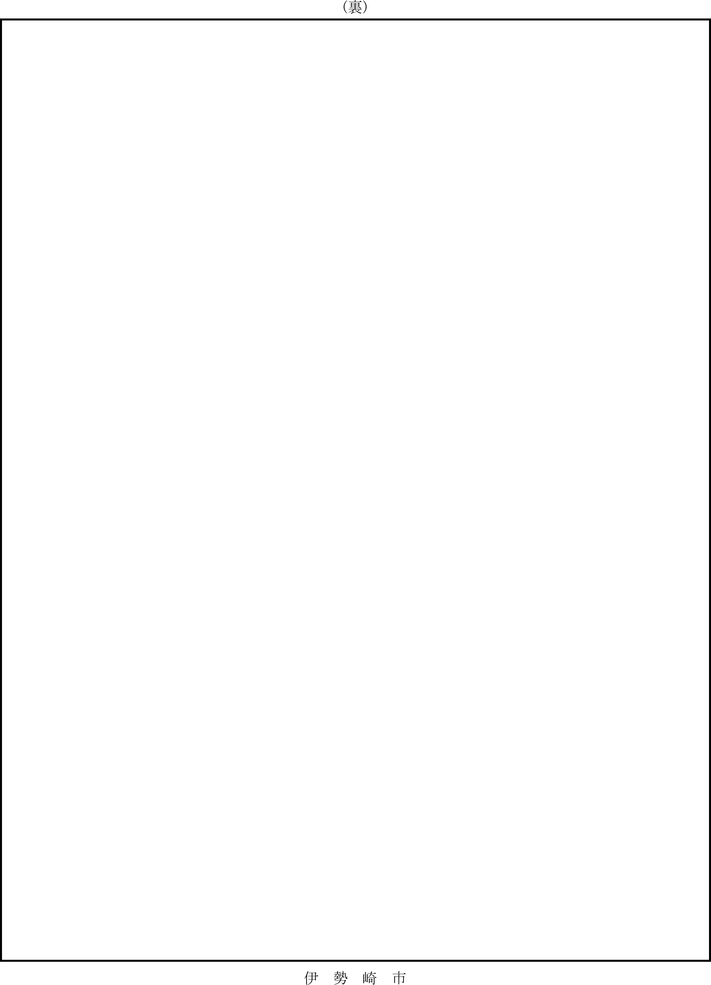
全部改正〔平成23年訓令甲5号〕、一部改正〔平成24年訓令甲4号・令和5年11号〕
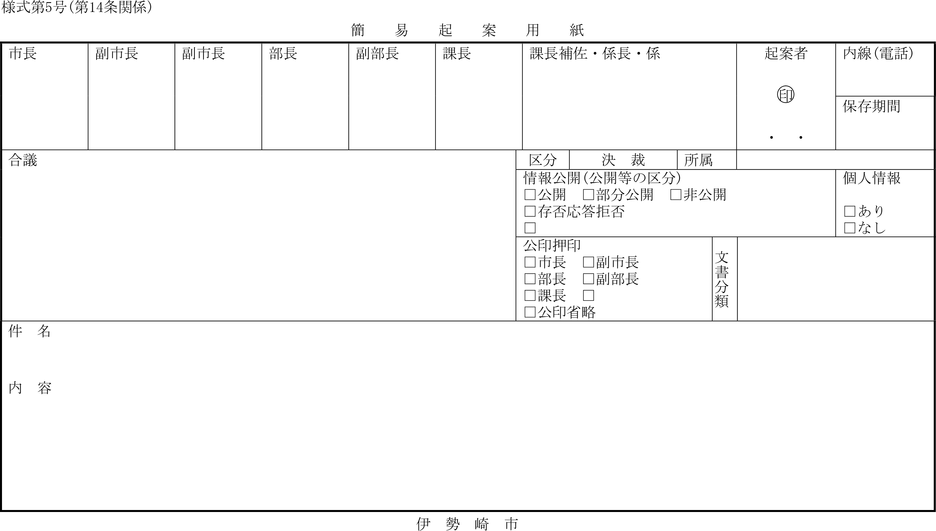
全部改正〔平成23年訓令甲5号〕、一部改正〔平成24年訓令甲4号・令和5年11号〕
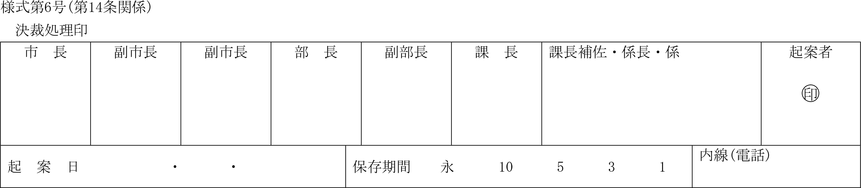
追加〔平成23年訓令甲5号〕、一部改正〔平成24年訓令甲4号・令和5年11号〕
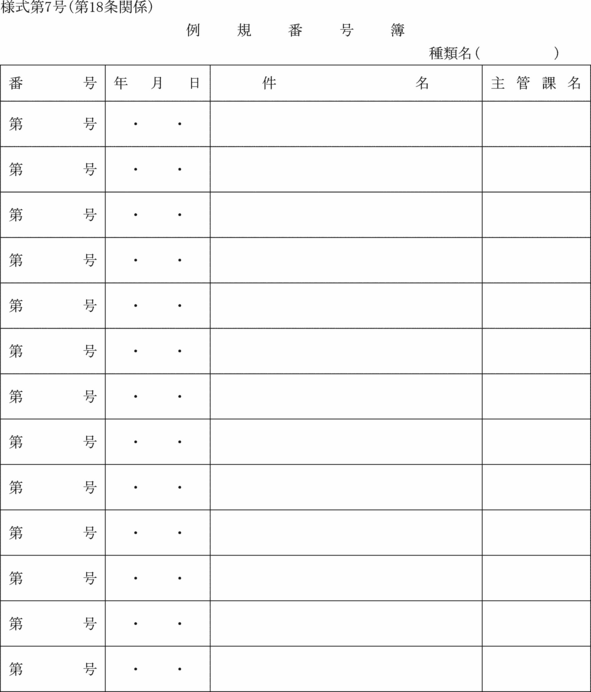
一部改正〔平成21年訓令甲2号・23年5号・24年4号〕
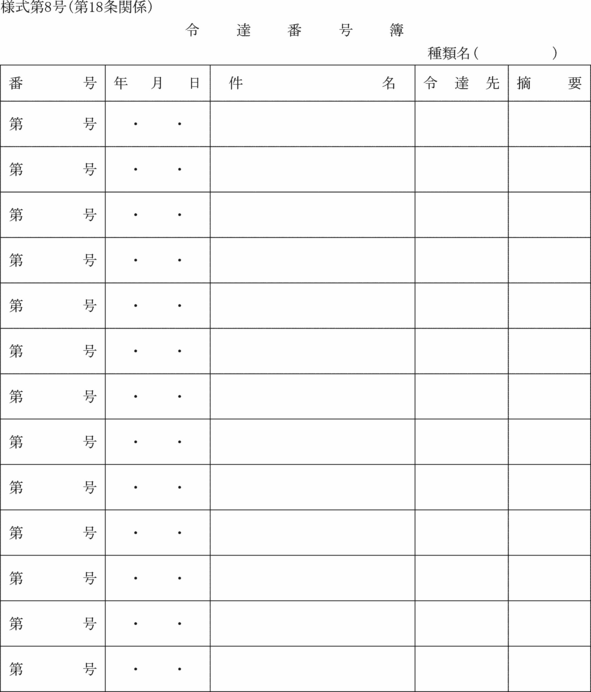
一部改正〔平成21年訓令甲2号・23年5号・24年4号〕
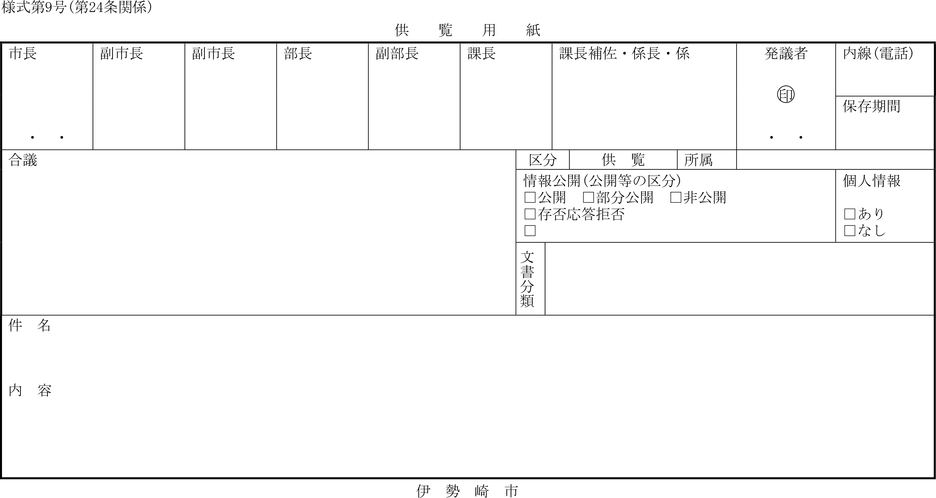
全部改正〔平成23年訓令甲5号〕、一部改正〔平成23年訓令甲5号・24年4号・令和5年11号〕
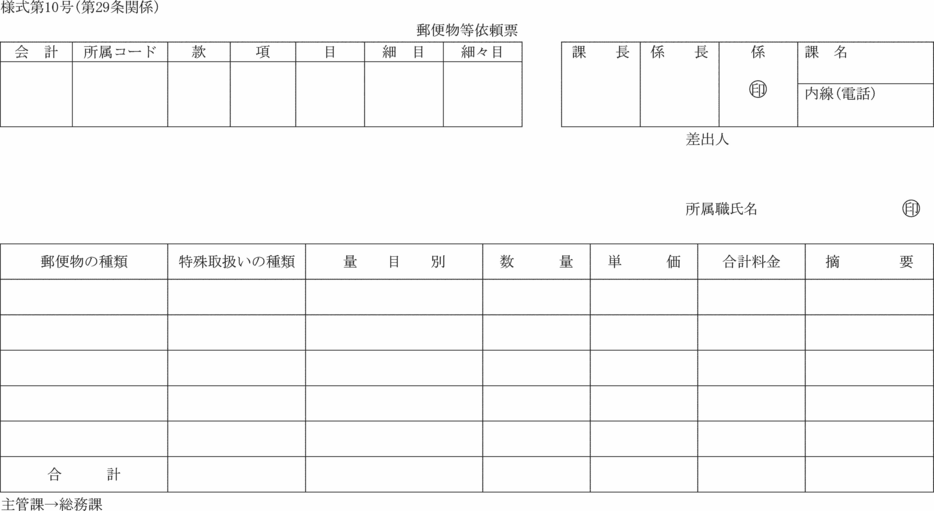
全部改正〔平成21年訓令甲2号〕、一部改正〔平成21年訓令甲2号・23年5号・24年4号〕

全部改正〔平成20年訓令甲3号〕、一部改正〔平成21年訓令甲2号・23年5号・24年4号〕
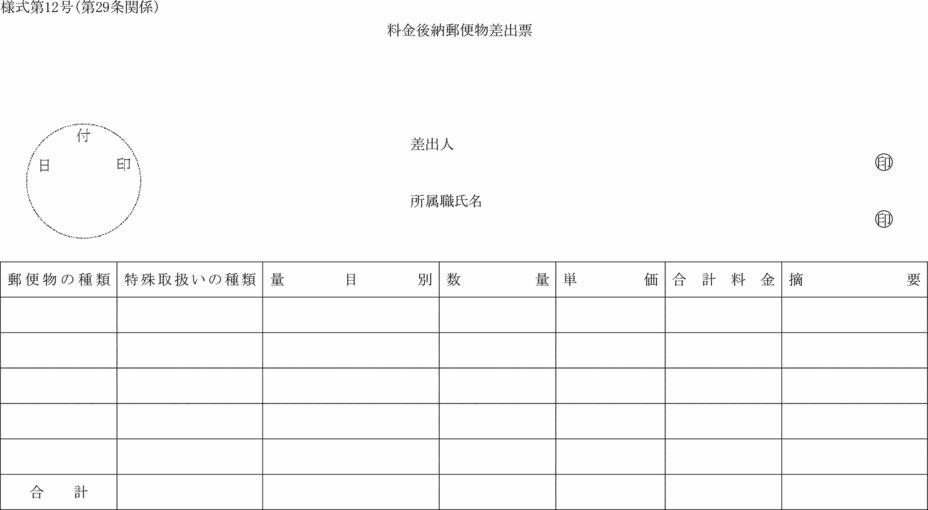
追加〔平成20年訓令甲3号〕、一部改正〔平成21年訓令甲2号・23年5号・24年4号〕

追加〔平成19年訓令甲19号〕、一部改正〔平成20年訓令甲3号・21年2号・22年2号・23年5号・24年4号〕
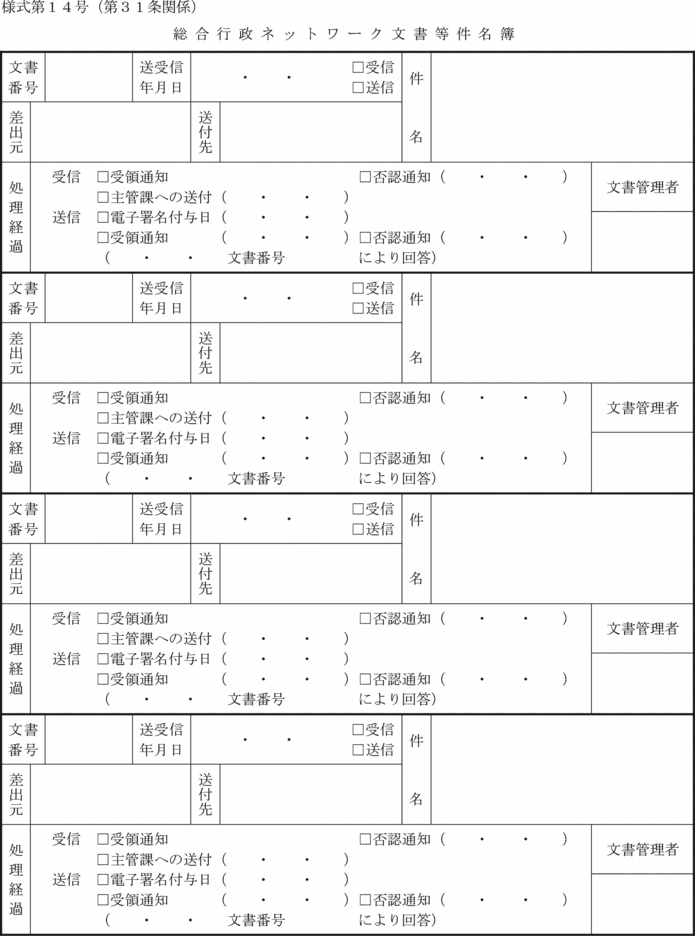
追加〔平成24年訓令甲4号〕
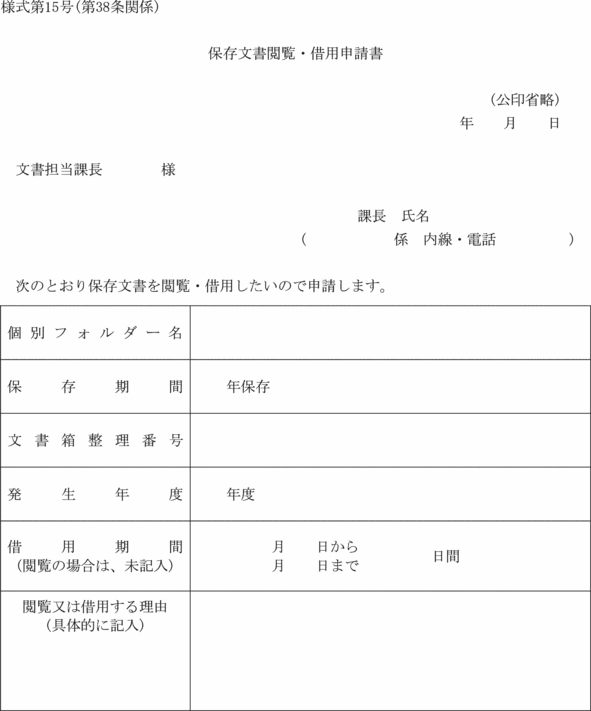
追加〔平成21年訓令甲2号〕、一部改正〔平成22年訓令甲2号・23年5号・24年4号〕
